最近、教員という立場から

果たして宿題は子どもにさせるべきなのか?
と考えることが多くなりました。
みなさんは子どもに宿題をするように促していますか?
私は現時点で「子どもに無理に宿題をさせる必要はない」と考えています。

宿題ってなんでやらないといけないの?
子どものときに考えたり、大人になって子どもから聞かれたことはありませんか?
あなたならこの質問に関してどのように答えますか?
「やりなさいと言われたからやる。」
「その日に学習したことを復習するためにやる。」
「テストでいい点をとるためにやる。」
「いい学校に行くためにやる。」
そんな感じでしょうか。
子どもの頃は上に挙げたような理由を大人から聞かされて、なんとなく言いくるめられていた方も多いと思います。
宿題をすることのメリット・デメリットについて考えたうえで、今一度宿題をすることの意味について考えていきたいと思います。
宿題をすることの2つのメリット
①学習の習慣が身に付く。
これは大きなメリットだと思います。毎日学習することが当たり前になるわけです。
学年が上がるにつれて宿題の量が増えるのが一般的ですから、学習習慣が身に付くことに加えて、学習時間の増加の効果も期待できます。
②学習内容が定着する。
その日にした学習を復習したり、同じ課題(教科書の音読など)を繰り返し練習したりすることで学習内容を定着させることができます。

宿題をすることの大きなデメリット
学習が嫌いになる。

毎日喜んで宿題をやってます!

算数の宿題が好きで、宿題に夢中です!
という子どもを見たことがありますか?
私は見たことがありません。
なぜでしょうか。
それは、宿題は先生から与えられた「受動的」な課題であるからだと考えます。
受動的とは、「自分の意志からでなく、他者から働きかけられて行動する」ことです。
この「受動的」というのが問題で、「宿題はやりたいからやる」のではなく、「宿題を出されたから仕方なくやっている」わけです。
現在日本の教育では、子どもたちに「主体的」に学ぶ態度を身につけられるように指導をしています。
主体的とは、「自分の意志や判断に基づいて行動する」ことです。
小学校の授業の中では、主体的に課題を見つけ、その解決に向かって学習していくことが目指されているわけです。
そのような態度を目指しているにもかかわらず、毎日「受動的」である宿題を出しているわけです。


じゃあ自主学習の宿題を出せばいいんじゃないの?
私も担任として自主学習の宿題を出すことがあります。
しかし、これも自主学習という名の「受動的」な宿題なのです。
自分から自主勉強をしようと思って取り組んでいるのではないという点で、「受動的」であると言えます。
私は最近になって、学習することの楽しさを知りました。

自分はお金のことについて全然わかっていない。税金や投資について知りたい。FPの資格取得を目指して勉強すればお金についての知識が身につくはずだ!
という思いから学習を始めました。
自分で言うのもなんですが、これが現在理想とされている「主体的な学習」だなと感じました。
結果FPの資格を取得することができたのですが、資格を取得することができた喜びよりも、自分の興味や関心に合わせて学習していくことの楽しさを知ることができた喜びの方が大きかったのです。

宿題という受動的な学習に取り組み続けると、学習とは、「させられるもの」、「したくないけどやるもの」というネガティブなイメージがついてしまうと感じます。本来学習とは「知らないことを知りたい!」「興味や関心のあることを追求したい!」というポジティブなイメージで捉えられるべきものであると思います。
ですから私は担任している子どもたちに無理に宿題をさせることはしていません。
休み時間に宿題をさせる先生もいますが、基本的にはさせません。
友達と遊びたい、話したいという思いが強いなかでさせることにあまり意味を感じません。

宿題をしなかったら頭が悪くなるんじゃないの?
たしかに、「宿題はしない。」かと言って「他の学習をするわけでもない。」
学習する機会が減り、テストの点数は下がるかもしれません。
でも、いずれ学習に向かっていくタイミングが訪れるはずです。
それは、

テストの点が下がってきた…これは勉強しないとまずいぞ…。
というような、さほどポジティブではない形かもしれませんし、

この戦国武将はかっこいいな。どういう生き方をしたのかもう少し調べてみよう!
↑小学校高学年でよくいる子ども
というような、興味や関心からくる形かもしれません。
「やりなさい!」
と言われてやるのではなく、「学習しなければならない」「学習したい」という気持ちが自ら起こってくるタイミングを待ってみませんか?

まとめ
宿題をすること自体に意味がないとは言いません。メリットでお話したように学習習慣を身につけたり、学習内容を定着させたりする価値は大きいと思います。
しかし、宿題に取り組むメリットよりも、宿題を「無理にさせることのデメリット」の方が大きいと考えます。
物事に興味や関心があるというのはすばらしいことです。そして興味や関心をもったことに取り組むときのモチベーションはとても高いです。無理に宿題をさせるのではなく、子どもが物事に熱心に取り組んでいる様子をあたたかく見守り、サポートしてあげることで、子どもたちが大人になっても学習を楽しめるようにしてあげたいという気持ちで子どもと接していきたい思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました。

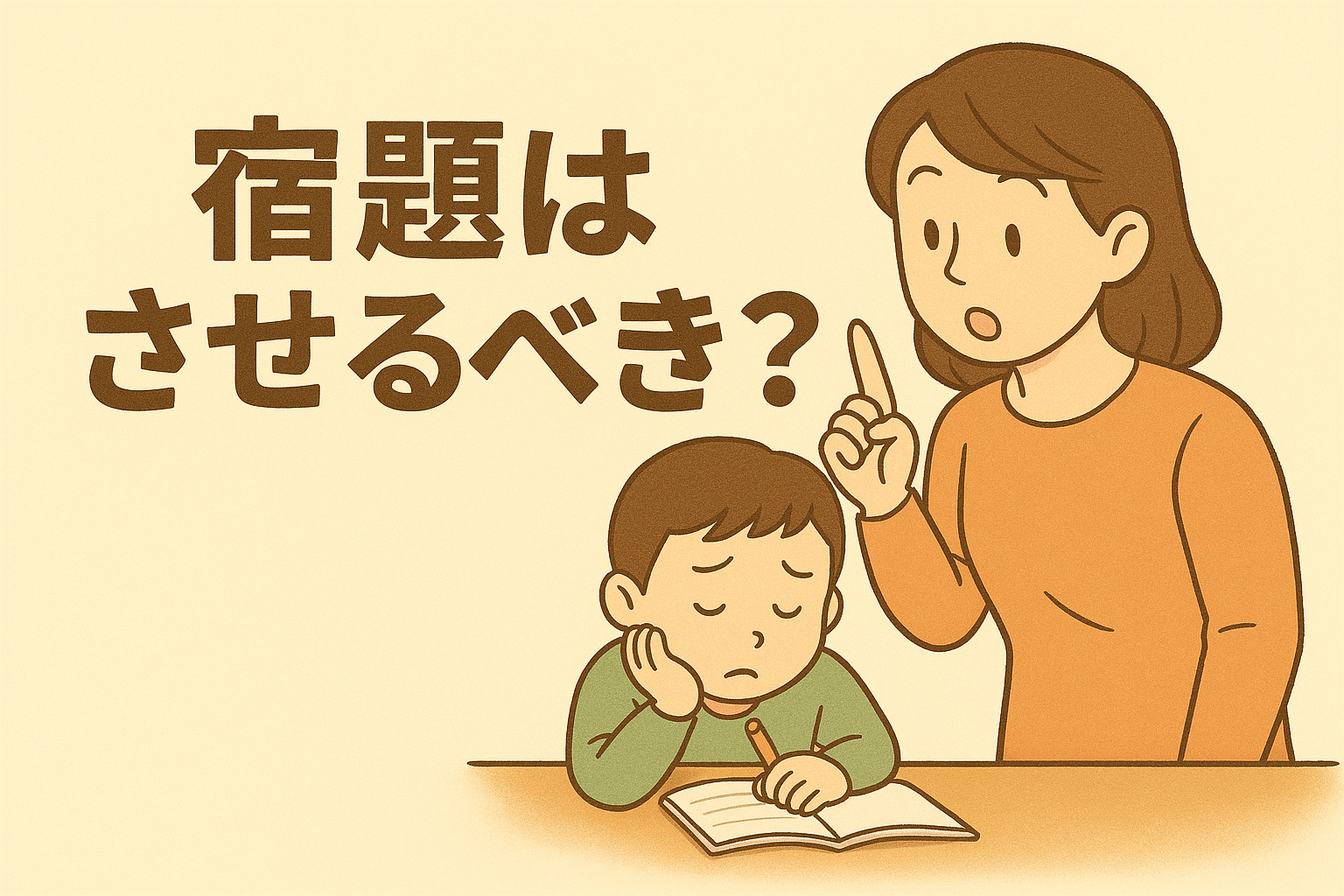


コメント