中学受験を控える保護者の皆さんにとって、内申書は気になる存在ですよね。
現役小学校教師として15年勤務し、6年生の担任を4回経験、中学受験が多い学校で数十通の内申書を作成してきた私が、実際の作成現場の本音をお伝えします。
この記事を読むことで、
「内申書に何が書かれるのか」
「内申書のどこが重視されるのか」
「保護者として教師とどのように関わるとよいのか」
がわかります。
中学校受験を控える保護者の方の参考になればうれしいです。
内申書の基本とは?(どんな項目がある?)
内申書(調査書)には、一般的に次の項目が含まれます。
◯基本情報:氏名・生年月日・小学校名など
◯出欠の記録:欠席・遅刻・早退の日数、長期欠席の理由
◯学習の記録(成績):各教科の評価(学校によって尺度は異なります)
◯行動の記録:生活態度、協調性、学習意欲など
◯特別活動:委員会・児童会・クラブ、ボランティア活動など
◯表彰・資格:校内外の表彰、検定合格など
◯所見(総合所見):担任が児童の性格や努力、長所・課題を自由記述する欄
※学校や自治体によって項目や書式が異なる場合があります。志望校の要項は必ず確認してください。
ズバリ!内申書で重視される最重要ポイント
私が最も力を入れて書く部分、そして内申書で重視されると考えているポイントは「所見」の欄です。所見には担任としての思いや観察が最も反映しやすく、その子の長所や努力の様子を具体的に伝えられる場所だからです。
正直なところ、学習の記録(成績)はあまり考慮されないと考えています。なぜなら、学習の記録は担任の主観で評価される部分もあり、学校によって成績のつけ方が甘い場合や厳しい場合など差があるからです。
では、教師はどのような子が内申書を書きやすいと感じるのでしょうか。
書きやすい内申書になる子の3つの特徴
「教師の印象に残りやすい子」は、結果的に書きやすい内申書になります。具体的には次のような子です。
- 授業で積極的に発言や質問をする子
授業時間は学校生活で最も長い時間を占めます。どの授業でも進んで発言や質問をする子は印象に残ります。
- 独自の意見や多様な考えを出そうとする子
三角形の面積の求め方を1通りで終えるのではなく、複数の方法を考えてノートにまとめたり発表したりする子は強く印象づけられます。
- 係活動や委員会活動で主体的に取り組む子
お笑い係として毎日コントを披露する、クイズ係としてスライドを作って発表するなど工夫を凝らす子は目立ちます。
また、委員会活動で「挨拶が減っているので挨拶運動をしよう」と課題を見つけ、解決のために行動する子も強く印象に残ります。
このような「目立つ活躍」をしなくても、
- 係や委員会を責任を持って続ける「責任感」
- 提出物やノートを丁寧に仕上げ、期限を守る「誠実さ」
- 誰にでも分け隔てなく接する「公平さ」
- 困っている友達を助ける「思いやり」
といった「日々の積み重ね」が結果的に印象を残すことも多いです。
一方で、特に目立つ行動が少なく平均的に見える子は、所見に書ける具体素材が少なくなり、担任として記述に苦労することもあります。
内申書を教師に依頼する際に気をつける3つのポイント
1.礼儀を意識する:最初の一言で好印象が伝わります
2.余裕を持って依頼する:締切間近ではなく早めにお願いする
3.感謝の気持ちを添える:「お願い」「ありがとうございます」を伝えるだけでも、教師のモチベーションにつながります
内申書の作成を依頼するときは、できるだけ余裕を持ってお願いすることが大切です。締切間近に依頼されると、担任としても十分に時間をかけて丁寧に書くことが難しくなります。また、依頼の仕方一つで、教師が受ける印象も変わります。
いつもお世話になっております。◯◯(志望校)を受験予定で、調査書の作成をお願いできますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
というような丁寧な言葉で依頼するとよいでしょう。
こうした配慮で、教師は安心して内申書に向き合うことができ、児童の様子をより具体的に丁寧に記述しやすくなります。
おわりに
内申書だけに過度に不安を抱く必要はありません。ただし、学力テストの結果が合否ラインぎりぎりだった場合に、内申書の内容が合否を分ける可能性があります。
同じ点数の受験生であれば、中学校が合格させたいのは「内申書の内容が印象的な子」です。
だからこそ、受験勉強と並行して、学校で主体性のある行動や日々の小さな積み重ねを大切にしていきましょう。
保護者の皆さん、どうか焦らずに。心から応援しています。

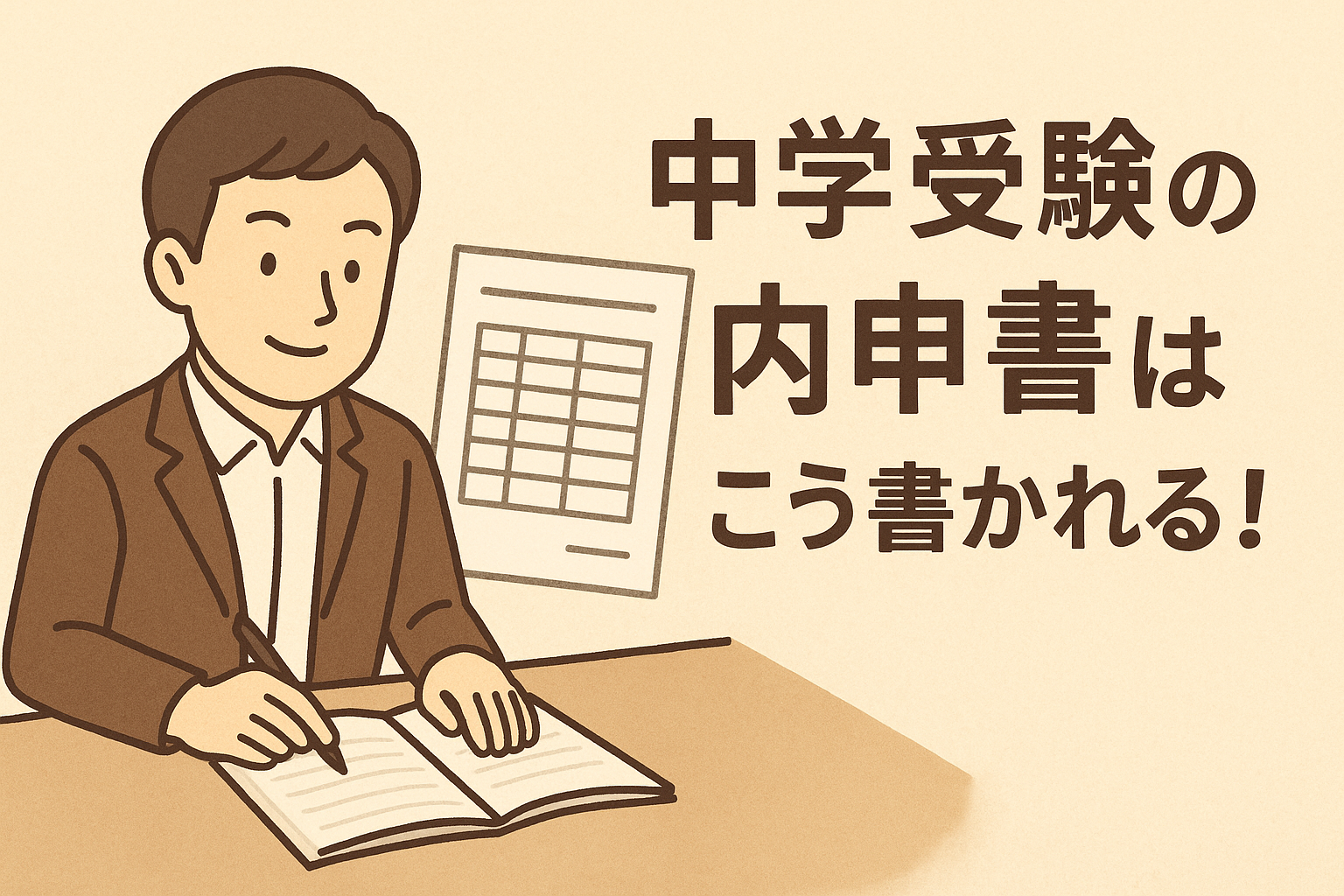


コメント